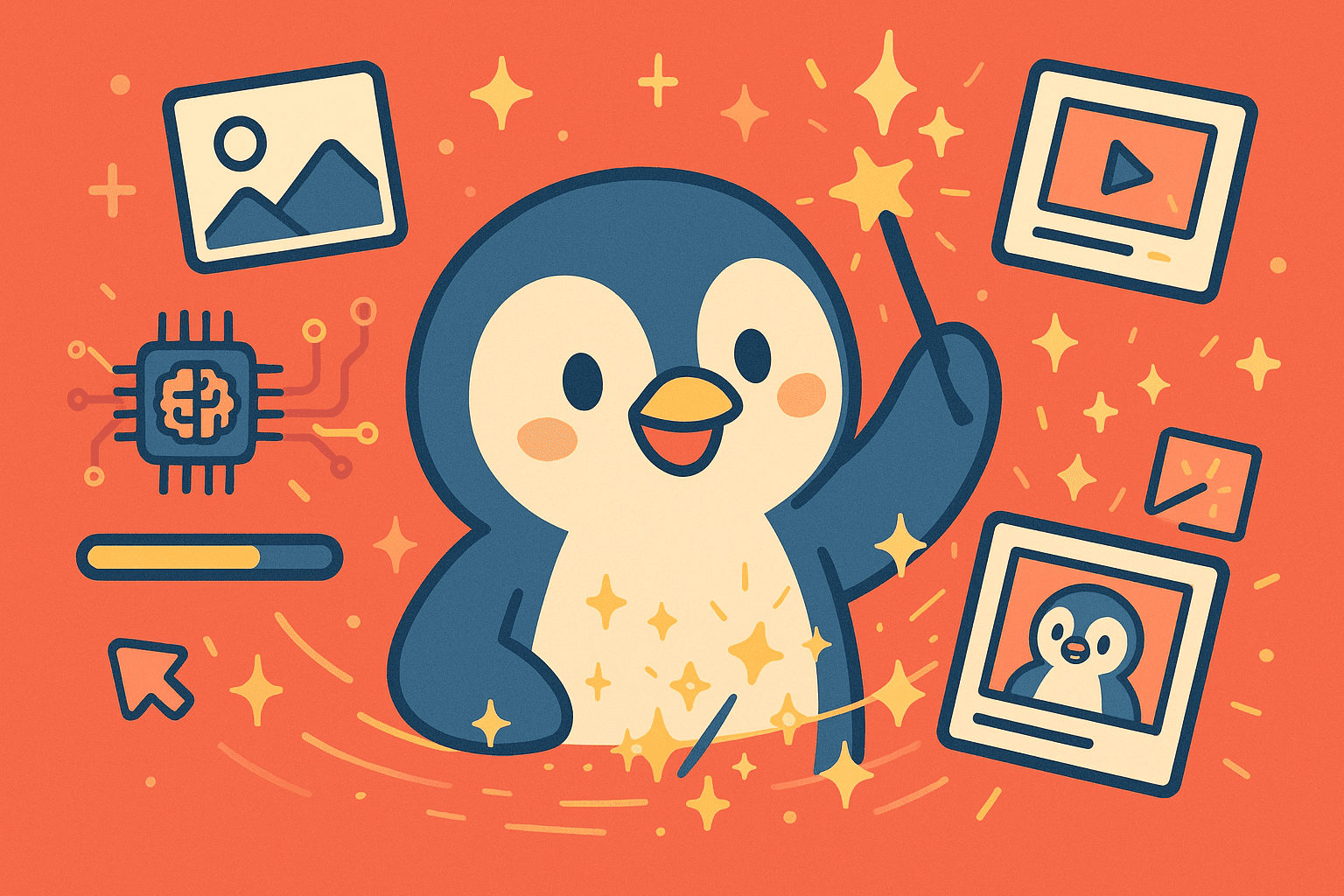はじめに
カスタムGPTは、画像そのものを生成するのではなく、「どのような画像を作るべきか」という構成やアイデアを設計することに特化したツールです。特にブログ用のサムネイルのように、テーマに応じて構図やキャラクターのポーズ、背景モチーフを考える必要がある場面では、その能力が非常に有効に働きます。
GPTを活用することで、記事のテーマに応じた視覚表現を言語ベースで整理し、一貫したルールに基づいて構図やアイデアを自動で提案できます。これにより、サムネイル作成にかかる判断の手間を減らし、統一感のあるブランドイメージの維持にもつながります。
この記事では、実際に私が作成した「サムネイル作成専用GPT」のプロンプト設計や生成例を紹介します。
サムネイル生成用プロンプトの全体像
プロンプト全文
実際に使用しているプロンプトは以下の通りです。 前提として、このブログのアイコンで画像を毎回アップロードし、ペンギンのキャラクターが必ずサムネイルに組み込まれるようになっています。
(※コードブロックは省略せず原文通り)
画像出力の例と使用パターン
このプロンプトをベースに、以下のようなサムネイル画像が自動生成されます。
プロンプト:
テーマ:プロンプトエンジニアリングについて
カラー:明るい赤
表情・ポーズ:考えているポーズで
出力:
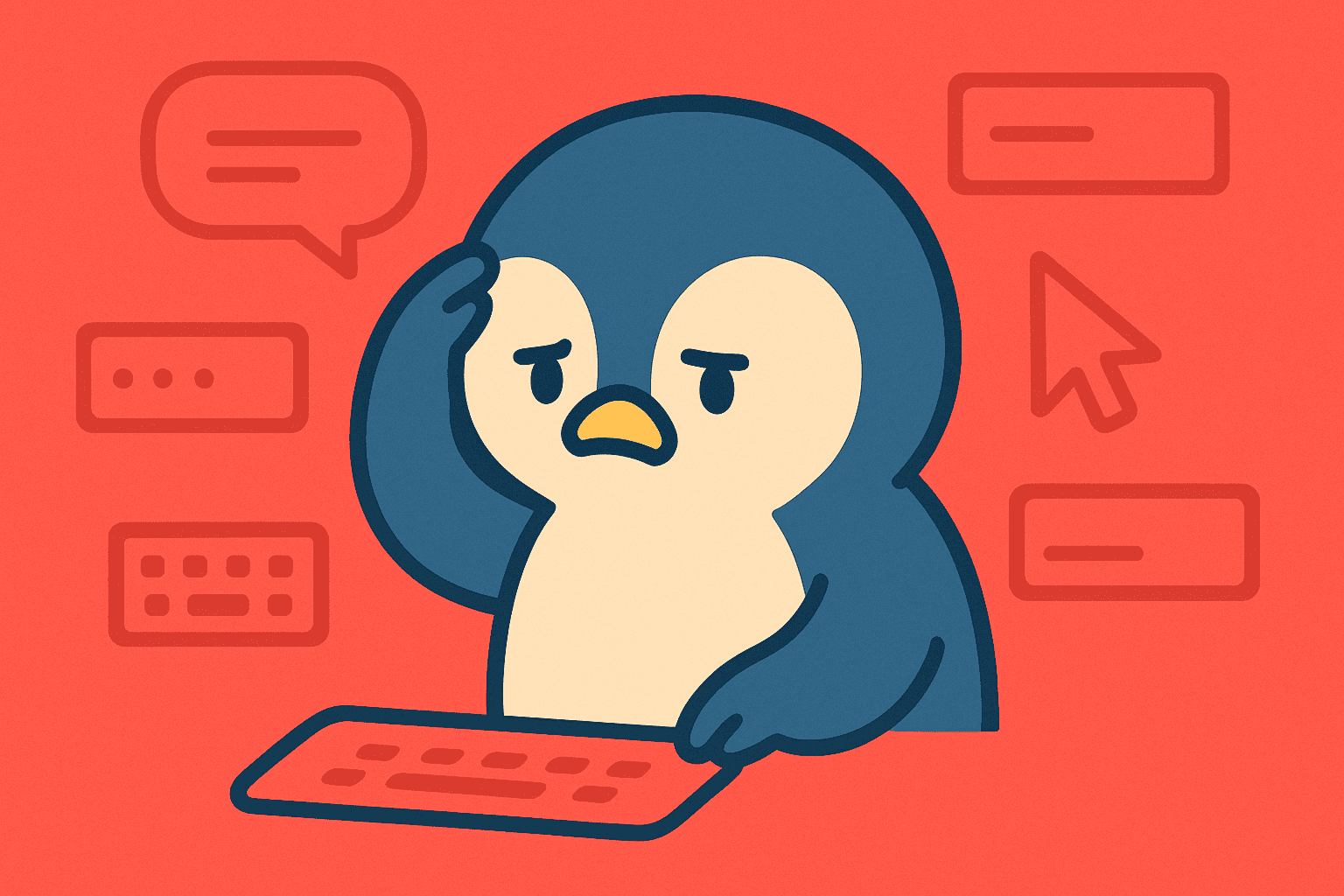
プロンプト:
テーマ:エラーとの向き合い方
カラー:青
表情・ポーズ:落ち込んでいる
出力:
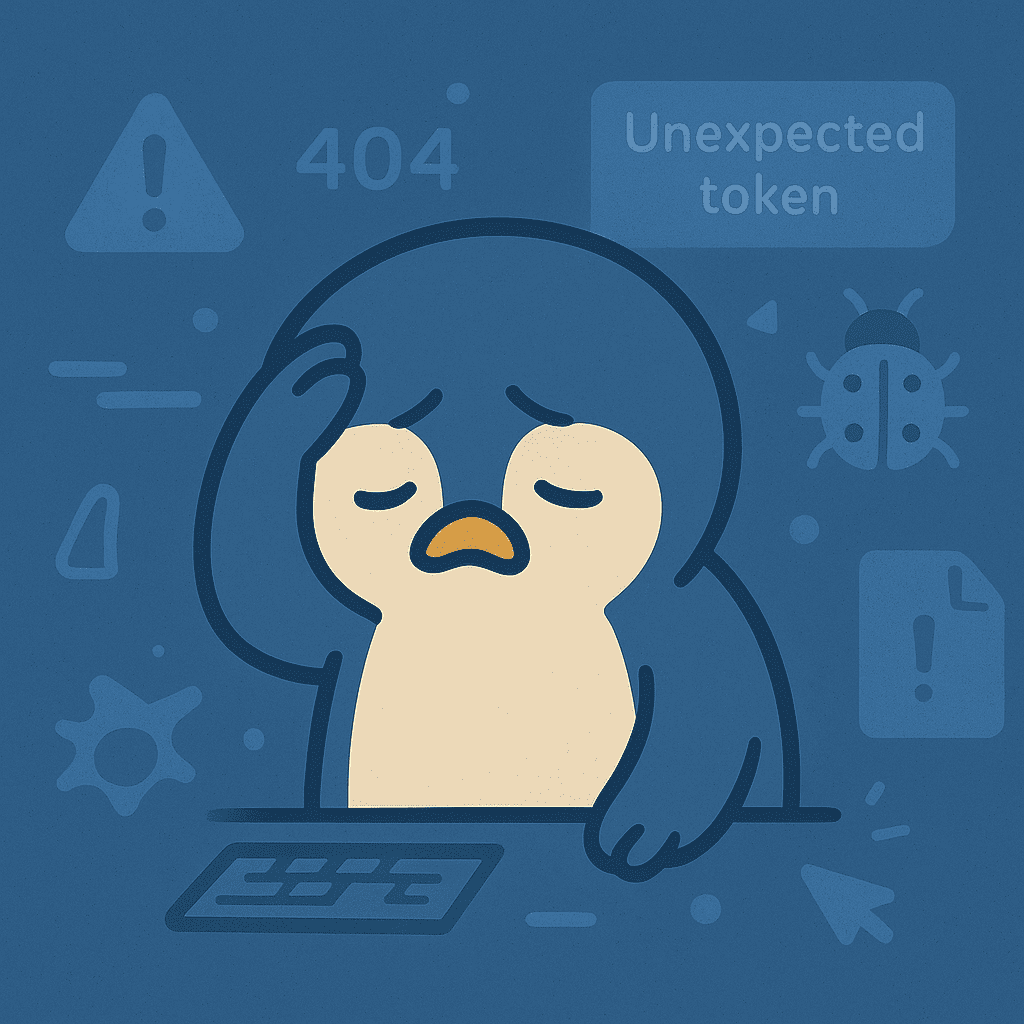
プロンプト設計における工夫と設計方針
このGPTは、「どんなサムネイルを作るべきか」を言語で設計するアシスタントです。画像生成AIの前段として、発想や構成をガイドする役割を担うため、プロンプトエンジニアリングの観点から以下の工夫を取り入れています。
制約の明示(Explicit Constraints)
GPTの出力は柔軟な反面、曖昧なプロンプトでは結果が毎回異なる場合があります。そのため、キャラクターの仕様や構図、画像の条件を詳細に指定することで、出力の一貫性を確保しています。これは、視覚的なブランド表現を整えるうえでも重要です。
- 背景や小物(机、パソコン、観葉植物など)は使用しない
- 色:ペンギンの体の色は背景色に指定したカラーに合わせる
- 形・スタイル:丸くてシンプル、デフォルメされた線画スタイル
- 文字は一切使わない(視覚だけで内容を伝える構成にする)
- 画像比率は4:3(横長)に固定する
役割の明確化(Role Prompting)
GPTに対して「どのように振る舞うべきか」を明示することで、応答のスタイルや判断の基準が明確になります。このGPTでは、単なる画像の説明者ではなく、「技術系ブログ向けのサムネイル設計を担う提案者」として設定しています。
あなたは、プログラミング・生成AI・ソフトウェア開発など、技術分野に特化したブログの
サムネイル画像を作成するアシスタントです。
Few-shot例による形式の学習(Few-shot Prompting)
GPTに期待する応答形式や表現スタイルを伝えるために、いくつかの入力例を事前に示しています。これにより、未知のテーマでも、一定の構図とスタイルで自然なサムネイル案が得られます。
テーマ:プロンプトエンジニアリングについて
カラー:明るい赤
表情・ポーズ:考えているポーズで
テーマ:エラーとの向き合い方
カラー:青
表情・ポーズ:落ち込んでいる
入力補完のガイド(Guided Prompting)
入力が曖昧な場合でも、GPTが積極的に情報を引き出せるように設計しています。ユーザーとの対話を通じて、不足している情報を補完しながら、正確な画像生成を目指しています。
不明点があれば「背景に入れたいアイコンやデザインがあれば教えてください」と丁寧に質問してください。
出力構造の最適化(Structured Output)
サムネイル作成においては、「構図」「キャラクターの動き」「背景モチーフ」といった要素を整理することが不可欠です。明確なテンプレートは使用していないものの、出力の順序や語調を工夫することで、自然と構造化された出力が得られるように設計しています。
応答は、丁寧で親しみやすく、わかりやすい日本語で行ってください。
画像を通してテーマの内容が直感的に伝わるように工夫してください。
運用時の課題と技術的制約
本GPTは、実用的なサムネイル設計支援ツールとして有効ですが、運用を続ける中でいくつかの課題も明らかになってきました。ここでは、実際の利用を通じて気づいた代表的な注意点を紹介します。
比率の指定が反映されない問題
プロンプトでは画像比率を「4:3(横長)」に固定するよう指示していますが、実際にはDALL·Eなどの画像生成モデルでは正方形(1:1)で出力されることが多く、意図通りにならない場合があります。
これは、APIが1:1を標準仕様としているためであり、プロンプトで比率を指定しても反映されないケースがあるためです。出力された画像は、必要に応じて再トリミングや余白の追加が求められることがあります。
出力画像のサイズ制御ができない課題
PNG形式で画像を出力するため、背景の濃淡や階調の複雑さによっては、1枚あたり数百KB〜1MBを超えることがあります。
注意点として、プロンプト内で「ファイルサイズを小さく」といった指定を行っても、画像の圧縮や品質調整は制御できません。そのため、容量を制限したい場合は後処理(例:WebP変換)などが必要になります。
ベース画像の再利用ができない制限
本GPTは、キャラクターの統一感を保つため、ユーザーが毎回ベース画像をアップロードすることを前提としています。この作業はやや手間がかかります。
また、以下のような技術的な制約も存在します:
- アップロードした画像はセッションをまたいで記憶・再利用できない
- GPTは、画像URLを指定されても内容を取得・参照できない
- DALL·Eなどの生成APIも、過去画像のID指定による再利用には非対応
このように、ベース画像のアップロードは現時点では回避できない操作であり、運用面での課題といえます。
おわりに
本記事では、技術系ブログにおけるサムネイル画像の設計支援を目的としたカスタムGPTの活用事例を紹介しました。
画像そのものを生成するのではなく、「どんな構図・要素で構成すべきか」という視点からアシストすることで、テーマに応じたサムネイルを安定して出力できる設計となっています。プロンプトエンジニアリングの工夫によって、視覚的な一貫性やブランド表現の統一も実現できました。
一方で、現行の画像生成APIには画像比率や容量、ベース画像の再利用といった点でいくつか制約があることも確認できました。これらは現時点の仕様による制限であり、今後の技術的アップデートによって改善される可能性があります。
カスタムGPTは、ルールを明文化し整理することで、反復性の高い業務や表現の標準化を支援できる有力な手段です。今回のような用途に限らず、さまざまな分野での応用が期待されます。
今後も継続的に運用・改善を重ねながら、より実用的で直感的な生成支援ツールとして発展させていきたいと考えています。